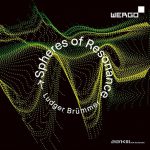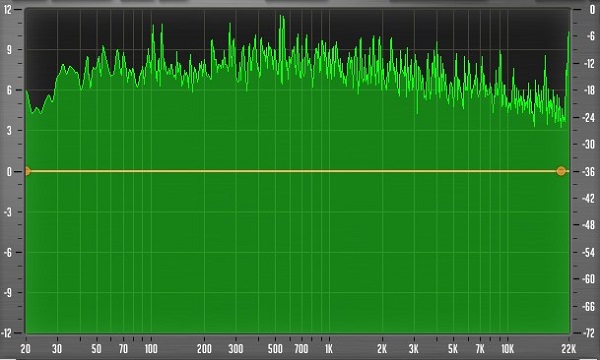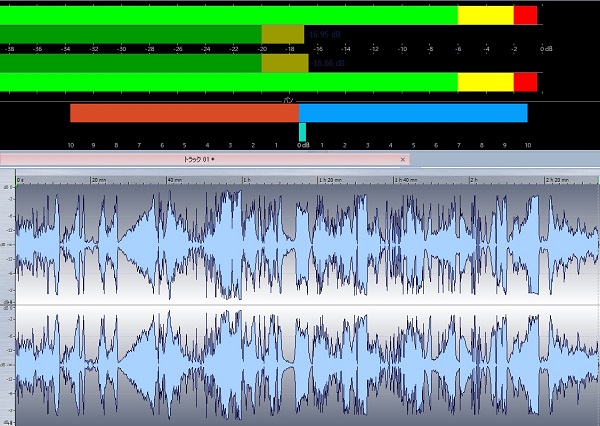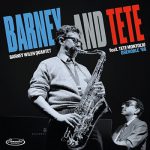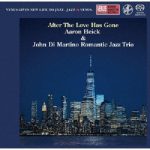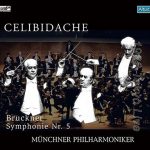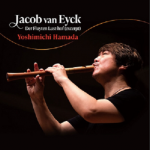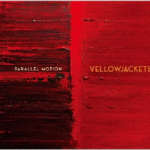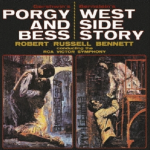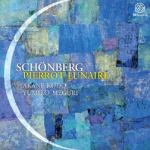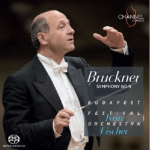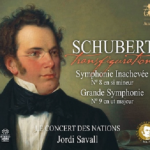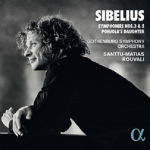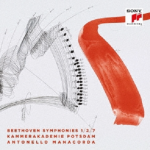漲る生命力!
ロウヴァリによるシベリウス第3弾は、難曲第3番と人気曲第5番の組み合わせ
世界各国で高い評価を得た第1番、第2番に続く、ロウヴァリとイェーテボリ響によるシベリウス交響曲全集の第3弾が登場。これまで第2番はレコード芸術誌2021年11月号「新時代の名曲名盤500」で同曲の第1位に、第1番は第2位に選出されています。今回はシベリウス転換期の重要作第3番と高い人気の第5番、そして第3番の前年に書かれた交響詩「ポヒョラの娘」を収録。これまでのアルバム同様、今回もテンポやダイナミクスの設定に個性的な解釈が聴かれますが、新鮮であると共に大きな説得力を持つことに驚かされます。
交響曲第3番はヘルシンキ郊外の豊かな自然に触発されたと言われる美しい作品ですが、その純朴な主題や展開は扱いがやや難しいところ。ロウヴァリは第1楽章冒頭の低弦から躍動的に歌わせ、その後も大きなメリハリを付けながら熱く迷いのない音楽を展開。それは、シベリウスの中後期交響曲の始まりとされるこの作品にの中にも息づく、初期作品に顕著であったロシア音楽の影響と、フィンランドの民族性を併せて強く認識させるものとなっています。また第5番はシベリウス自らの50歳を祝う演奏会のために作曲された祝典的な内容で、近年特に人気のある作品。ロウヴァリはここでもオーケストラをたっぷりと鳴らしてクライマックスを形作り、作曲家が、頭上を16羽の白鳥が旋回する様の美しさに触発されたと語った自然描写を雄大に描ききっています。何曲も書かれるうち、長さも楽器編成もどんどん小さく濃密になっていったシベリウスの交響曲に対して、比較的大規模な編成で書かれ続けた交響詩ですが、ここに収録された「ポヒョラの娘」も三管編成。フィンランドの民族抒情詩『カレワラ』に登場する英雄ワイナミョイネンと、彼が出会ったポヒョラの娘の物語を、ロウヴァリは活き活きと描いています。
国内仕様盤日本語解説…鈴木淳史(ナクソス・ジャパン)
 【TOWER RECORDS ONLINE】
【TOWER RECORDS ONLINE】