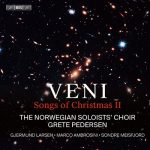stereo誌 2023年02月号 今月の変態ソフト選手権!/A Soul to Claim
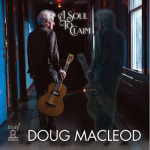
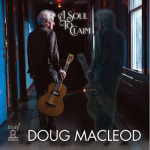
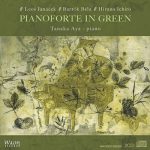
自然と静けさから生み出される破格のパワーに満ちた音楽
丹後の宮津出身のピアニスト、田中綾による、ヤナーチェク、バルトーク、平野一郎作品集。タイトルの「ピアノフォルテ」はフォルテおよびピアノの表現であり、グリーンとは、ハンガリーや現在彼女が移住している滋賀県蒲生群の農村の景色。田中はコダーイ音楽研究所に留学していた経歴を持ち、また、とくに歌(合唱)との共演も多く、彼女が奏でるピアノはオーケストラのような音響と音色で鳴り響きながら、人の声のように様々な情動を聴き手によびおこさせる、濃厚なもの。
演奏会のとき、ステージ袖から登場するのではなく、どこからともなく裸足で現れ、今その瞬間に生まれたように音楽を奏でていきます。精巧に調律されたピアノで、1ミリの狂いもないタッチで、作曲者たちが音符に込めた色や風景、作曲家の心情までをも浮かび上がらせていきます。その音色をCDにするために、今回384kHz 24bitによる編集が行われました。ホールの空気から、音符ひとつひとつから立ち上る様々な香りや風景、そして作曲家たちの声がなまめかしく聴きとれる、究極の2枚組となっています。
(ブックレットより抜粋)ヤナーチェク、バルトーク、平野一郎という作曲家たちは、それぞれ生まれた場所も年代も異なりますが、古くから伝わる文化が危機にさらされる難しい時代の中で、自分たちの真の音楽を探求しているというところで繋がっています。小さな村の歌や踊りを深く研究するうちに、それぞれに独自の作曲語法を生み出し、命がけで守らなければ永遠に忘れ去られてしまうあらゆる声を、楽譜に刻んでいきました。彼らの楽譜を開くと、草原や海辺の原風景とそこに暮らす人々、ひそんでいる小さな生きもの、そしてもっと前からそこにいたであろう、目に見えないものたちが飛び出してきます。暗闇に消えかけていたかすかな灯りが、蛍の光のようにぽつぽつと点り、皆さんの心にひろがっていきますように。―田中綾ー
(1/2)(キングインターナショナル)
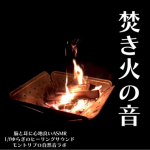
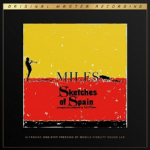
マイルス・デイヴィス 1960年発売『Sketches of Spain』をモービル・フィデリティ社の究極のアナログ盤規格「ULTRADISC ONE-STEP」×「MoFi SuperVinyl」で復刻。
1960年作品。スペインをモチーフにギルとマイルスのコラボレーションが作り上げた音世界の傑作。作曲家ホアキン・ロドリーゴがクラシック・ギターのために書いた「アランフェス協奏曲」は、このアルバムで演奏されたことによって幅広いリスナーやミュージシャンに広まった。ドラマティックなメロディ、そして哀愁と熱情に満ちたオーケストラ・サウンド。
「ULTRADISC ONE-STEP」(UD1S)シリーズ
独自のテクノロジーとマスタリング技術、そして贅沢な時間を駆使し、マスター・テープのデータを限界まで引き出したハイ・クオリティな復刻盤により世界中のオーディオファンから高い評価を得ているモービル・フィデリティ・サウンド・ラボ社より、究極のアナログ盤規格「ULTRADISCONE-STEP」(UD1S)シリーズが登場。標準的なアナログ盤の生産工程である、ラッカー盤から完成品までの「スリー・ステップ・プロセス」から2工程を省き、あくまで音質を重視した「ワン・ステップ・プロセス」を実現。生産工程で発生するノイズを最小限に抑え、音のディテールの再現性とダイナミクスを大幅に向上させている。「音楽は可能な限り原音に忠実に再現されなければならない。」という、モービル・フィデリティ社設立以来の基本ポリシーを文字通り実現した、究極のアナログ盤規格である。
「MoFi SuperVinyl」
MoFi SuperVinylは、アメリカ・カリフォルニア州のNEOTECH社とRTI社の共同開発により新たに生み出された独自のアナログ盤素材。新たに開発されたカーボンレス染料(半透明)により、オリジナルのラッカー盤と区別がつかない、より精密な溝の製造を可能にし、マスタリング・スタジオのサウンドに限りなく近い音質を再現する。(発売・販売元 提供資料)

リファレンススピーカーは、FE108SS-HPのスーパースワンを使用してます。
FE108-solのスーパースワンを試聴する機会がありました。
低域の量感と厚みはFE108SS-HPがあり、反応の良さときれはFE108-solの方があります。
今回、FOSTEXのホーンツィーターを載せた場合、どの位変化するか試してみたかったので
T96A-SAを載せて試聴(0.47㎌逆相)。音場の広がりと低域の締まりが出ました。
悪乗りして、重石替わりにT500A MKⅢ(0.22㎌逆相)で試聴。
T96A-SAに比べ音の品位が違う。反応が良いユニットだけに違いは明確に表れ、倍音域の表現力
(弦の艶)、クリアなヴォーカル、音場の広がり。今までに聴いたことのないスーパースワン。
FE108SS-HPに載せて聴いてみたいが、この様な聴き方をするのは私しかいないかも?
ユニットより10倍近く価格差のあるホーンツィーター、まさに変態。
聴かなければよかった。
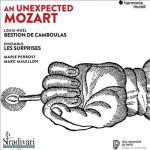
[グラスハーモニカ]
1743年、アイルランド人のパッカリッジが水を入れた脚付きグラスの縁をこすって音を出し演奏することを思いつきます。その後1761年にグラスハーモニカは楽器として完成をみます。20~54個(37が標準サイズ)のグラス(器)が棒に、互いに接触しないようにはめあわされ、器の直径によって音高が決まります。奏者は濡れた指でグラスの縁をこすって演奏します。この楽器は、この音色が動物を怖がらせる、あるいは屈強な男が1時間で倒れる、演奏者を発狂させる(当時の原料の40%が鉛ガラス)といった理由で、ドイツのいくつかの都市で禁止され、1835年に姿を消すこととなります。が、パガニーニはこの楽器を「天使のオルガン」と呼び、モーツァルトのほかにもベートーヴェン、ドニゼッティ、R.シュトラウスらもこの楽器のために作品を書きました。ここで演奏されている楽器はガラス工芸の巨匠ゲルハルト・フィンケンバイナーによるもので20世紀後半に製造されました。演奏しているトーマス・ブロッホは、数少ないプロ奏者として活躍する人物です。
[スクエア・オルガン]
ピアノ=オルガンとも呼ばれ、オルガンとピアノの機能をあわせもつ楽器。オルガンとして、ピアノとして、あるいはオルガンとピアノの両方の機構を同時に鳴らすこともできる楽器です。(キングインターナショナル)

ヴァイオリンと合唱版 ローリゼンの「おお、大いなる神秘」!
独自の音楽世界を突き進むアン・アキコ・マイヤース最新盤!
ローリゼンの傑作「おお、大いなる神秘」の新ヴァージョン!
そしてバッハの3つの人気曲をカップリングしたミニ・アルバム!
40枚目のアルバム「シャイニング・ナイト」がレコード芸術「特選盤」に選ばれるなど、独自の音楽世界を華麗に突き進んでいるアメリカのスーパースター・ヴァイオリニスト、アン・アキコ・マイヤースのAvie最新盤。ロサンゼルス・マスター・コラール、指揮者グラント・ガーション、作曲家モーテン・ローリゼン(モートン・ローリゼン)とともに、ローリゼンの合唱曲の傑作「おお、大いなる神秘(オー・マニュム・ミステリウム)」新ヴァージョン(ヴァイオリンと合唱版)を製作! そして、バッハの3つの人気曲「主よ、人の望みの喜びよ」、「羊は安らかに草を食み」、「目覚めよと呼ぶ声あり」のヴァイオリンと合唱版(いずれも世界初録音となるニュー・アレンジ)の計4曲をカップリングしたミニ・アルバムが登場。神秘的でどこまでも美しく、心洗われるローリゼンとバッハの響きをご堪能ください。
ドイツ系アメリカ人の父親と日本人の母親の間に生まれたアン・アキコ・マイヤースは、11歳でロサンゼルス・フィルと共演し以降世界中のトップ・オーケストラと共演。複数のアルバムが米ビルボードのクラシカル・チャートで第1位に輝き、2014年にはビルボードのもっとも売れているクラシック器楽奏者にも選ばれています。(東京エムプラス)
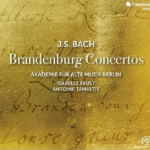
ベルリン古楽アカデミーのブランデンブルク協奏曲!これだけでも心躍るのに、なんとイザベル・ファウストとアントワン・タメスティという世界的名手がゲストに登場しているという、前代未聞のスケールの録音の登場です。ベルリン古楽アカデミーは1998年にブランデンブルク協奏曲を録音(HMM 931634)、以降幾度となく演奏会でも取り上げており、まさにかれらの手中に完全に収められたもの。自由自在、余裕たっぷりにあそびのあるアンサンブルが展開されております。また、ファウストとはバッハのヴァイオリン協奏曲集(KKC 6219/ HMM 902335)で素晴らしい録音を成し遂げ、タメスティともテレマンの協奏曲プロジェクトでお互いをよく知り尽くした上でのレコーディングとなっております。
ファウスト、タメスティ両名が参加している第3番では終楽章の目もくらむようなスピード感で展開されるパッセージが圧巻!ファウストが参加している第4番はリコーダーが活躍する楽曲ですが、ファウストの攻めに攻めた、典雅で超絶技巧のパッセージもまた聴きもの。第6番はヴァイオリンが含まれない少し珍しい編成の作品ですが、ヴィオラのタメスティの存在感が際立っています。ほかにもアルパーマンの雄弁すぎるチェンバロや、管楽器の面々のうまさ!語りつくせぬ聴きどころの連続ですが、まるで6曲全体がひとつの大きな組曲であるように感じるくらい、ひといきに聴いてしまいます。作品当時の奏者たちも高い技巧の持ち主だったことは夙に知られるところですが、あらためてその史実に驚きとともに思いをはせると同時に、当時の演奏の現場の熱気と活気、そして聴衆たちの興奮までもが再現されているよう。即興感と心地よい疾走感に満ちた、尋常ならざる熱気とエネルギーと気魄にみなぎった演奏です。
(キングインターナショナル)
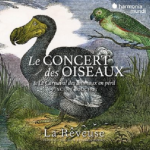
<div>

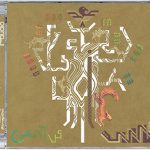
ヘンニング・ソンメッロ Henning Sommerro(1952-)の《牡鹿》は、古代北欧語の詩集『エッダ』の「グリームニルの歌(Grimnismal)」の一節をテクストに作曲された作品です。「四頭の牡鹿もいて、彼らは首をうしろにまげ、樹の皮から若芽をむしって食べている……」。ザ・リアル・グループのメンバーだったアンデシュ・エーデンロート Anders Edenroth(1963-)の《樹の歌》は、神話の「樹」を現代の気候変動になぞらえて作詞作曲されました。マリアンネ・ライダシュダッテル・エーリクセン Marianne Reidarsdatter Eriksen(1971-)は、第二次世界大戦で荒廃した土地に樹を植える女の姿に希望を見るハルディス・モーレン・ヴェソース(1907-1995)の詩に作曲。美しいメロディで知られるシンガーソングライター、エルルン・ユースタ Ellrun Ystad(1965-)の《母に捧げる三つの詩》もヴェソースの詩に作曲されました。
クリスティーン・ドンキン Christine Donkin(1976-)は、合唱に対する挑戦的な姿勢が刺激的だ、とカントゥスのメンバーがいう、カナダの作曲家です。世界樹を語る《円》は、カントゥスが彼女から求められて歌詞を書いた作品です。アメリカのエリック・ウィリアム・バーナム Eric William Barnum(1979-)は、2曲。スウェーデンの詩人ヴィクトル・リュードベリ(1828-1895)の詩に作曲された《ユグドラシル》とアメリカのサラ・ディーズデール(1884-1933)の詩による《満天の星》。ラグナル・ラスムセン Ragnar Rasmussen(1966-)の《天の砦を知っている》は、ノルウェー民謡をアレンジした作品です。トリュグヴェ・ブロスケ Trygve Broske(1973-)の《ラタトスクル》は、鷲のことばを運ぶためにユグドラシルの上をかけまわるリスを描いたアリス・メージャー(1949-)
の詩に作曲されました。(キングインターナショナル)

国際連合創設50周年を記念してショルティが結成した楽団ワールド・オーケストラ・フォア・ピースとの1995年の記念コンサートがCDとDVDに収録されています。
モーツァルトの『レクイエム』は作曲家の没後200年を記念して、ウィーンの聖シュテファン大聖堂で行われたミサのライヴ録音です。
ショルティ最後のライヴ録音はチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団とのマーラーの交響曲第5番でした。
ジョン・トランスキーによりプロデュースされたオーディオ・ドキュメンタリー(CD 45)にはアンジェラ・ゲオルギュー、キリ・テ・カナワ、クレメンス・ヘルスベルク(ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の元ヴァイオリニスト・楽団長)、マイケル・ハース(元デッカ・プロデューサー)、チャールズ・ケイ(ワールド・オーケストラ・フォア・ピースの理事)などの関係者たちが参加しています。
アンドリュー・スチュワートによる新規解説が掲載された80ページのブックレット(英語・フランス語・ドイツ語)付き。オリジナル・ジャケット仕様。(ユニバーサル・ミュージック/IMS)
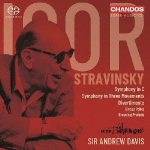
名匠アンドルー・デイヴィス! 迫真のストラヴィンスキー!
多数のオーケストラや音楽祭などで主要なポストを務めてきた巨匠アンドルー・デイヴィス!
激動の時代に作曲された、ストラヴィンスキーの名曲を振る!
イギリス音楽を得意とし、BBC交響楽団、メルボルン交響楽団などの音楽監督を務めてきたイギリスを代表する指揮者、アンドルー・デイヴィスによるストラヴィンスキー!
ストラヴィンスキーの「春の祭典」や「ペトルーシュカ」を初演したピエール・モントゥーの80歳の誕生日を祝った「グリーティング・プレリュード」から始まり、大半がパリで書かれ、作曲当時妻と娘を失うというストラヴィンスキーにとっては非常につらい時期に作曲された「交響曲 ハ調」(シカゴ交響楽団創立50周年記念委嘱作品)が収録されています。また、ニューヨーク・フィルハーモニックから委嘱され、第2次世界大戦を伝える映像を観たことに影響されたという「3楽章の交響曲」など激動の時代に作曲された作品を多く集めた今作。これまでに多数のオーケストラや音楽祭などで主要なポストを務めてきた巨匠アンドルー・デイヴィスが卓越したタクトでストラヴィンスキーの名曲を奏でます。(東京エムプラス)
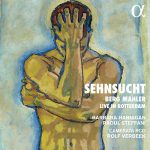
小編成と無観客、パンデミックの時代ならではのライヴで聴く、ウィーン世紀末
主にオランダで指揮者、編曲者として活躍しているロルフ・フェルベークと、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の団員で組織される室内アンサンブル、カメラータRCOによるベルクとマーラー。ベルクの『初期の7つの歌』では、ピアニストとして活躍したレインベルト・デ・レーウがオリジナルのピアノ譜から編曲した版(作曲者自身による管弦楽版も参考にしていると思われます)、『4つの歌曲』はオランダ放送フィルの打楽器奏者であり、デ=メイ「指輪物語」の管弦楽編曲などでも知られるヘンク・デ・フリーヘルによる版を使用。マーラーの交響曲第4番は、シェーンベルクの弟子であったエルヴィン・シュタインが「私的演奏協会」のために編曲したもの。ソリストを務めるのは後期ロマン派、新ウィーン楽派から同時代音楽までのスペシャリストであるバーバラ・ハンニガンと、オランダの若きバリトン、ラウル・ステファニ。2020年からの世界的パンデミックの中で、様々な管弦楽作品を小編成のカメラータRCOのために編曲してきたというフェルベークとアンサンブルの意思疎通は非常に親密なもので、ハンニガンらも奥行きのある表情でこの秀演をさらに表現豊かなものにしています。このアルバムはロッテルダムのデ・ドゥーレンにて収録されたストリーミング用無観客公演の様子を収めたもの。今の時代ならではのライヴ・パフォーマンスと言えるでしょう。
国内仕様盤 解説・歌詞訳…広瀬大介(ナクソス・ジャパン)
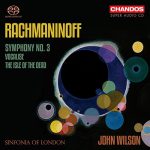
ジョン・ウィルソン&SOL! ラフマニノフの交響曲第3番!
ジョン・ウィルソン&シンフォニア・オヴ・ロンドン、次なるリリースはラフマニノフ!
交響曲第3番の卓越した管弦楽法を余すところなく引き出した名演!
3年連続となるBBCミュージック・マガジン賞受賞(「デュティユー:バレエ音楽 《狼》」〔RCHSA5263/CHSA5263〕、「レスピーギ:ローマ三部作」〔RCHSA5261/CHSA5261〕、「コルンゴルト:交響曲嬰ヘ調」〔RCHSA5220/CHSA5220〕)や、2021年のBBCプロムスでの初コンサートの世界的な評価で著しい躍進を続けるジョン・ウィルソンと、彼が再結成した”シンフォニア・オヴ・ロンドン”、次なるリリースは「ラフマニノフ」!
スイスの画家アルノルト・ベックリンの油彩画を題材にした「死の島」、愁いを帯びた名旋律が様々なアレンジで広く親しまれている「ヴォカリーズ」と組み合わせこのアルバムのメインに据えたのは、ラフマニノフ晩年の傑作として名高い「交響曲第3番」。1917年に起こったロシア革命によりアメリカへ亡命したラフマニノフは、多忙な演奏活動、指揮活動のため思うように作曲に専念できず、亡命後から世を去るまでの25年間で書いた管弦楽作品はわずか4曲にとどまります。そんな中スイスのルツェルン湖畔に構えた別荘で大部分が書き上げられ1936年に完成した交響曲第3番は、有名な交響曲第2番やピアノ協奏曲第2番で見られたようなロシアらしい甘美でロマンチシズム溢れる曲風からはやや離れ、より複雑で洗練された管弦楽法が際立つ作曲家人生の集大成ともいえる作品です。ジョン・ウィルソン&SOLは煌びやかな管楽器、しなやかな弦のサウンドを存分に活かし、彼らならではの豊かな色彩感でこの傑作の魅力を余すところなく引き出しています。(東京エムプラス)

名ソプラノ歌手、ディアナ・ダムラウによる、ゴージャスで美しき至福のクリスマス
超絶技巧と”銀の美声”といわれる声を持つ人気の歌姫ディアナ・ダムラウ。2011年6月には、東日本大震災の直後で外国人演奏家のキャンセルが相次ぐ中、「苦しい時にこそ音楽を」と、当時1歳の息子とベビーシッターを伴って来日、メトロポリタン・オペラの引っ越し公演を大成功に導き、日本での人気が高まりました。現在、最も世界的な活躍をしているドイツ出身の名ソプラノの一人。リリック・ソプラノからコロラトゥーラ・ソプラノまで、そのレパートリーは幅広く、《ランメルモールのルチア》、《マノン》、《椿姫》、《リゴレット》のジルダ、《魔笛》の夜の女王などで、ミラノ・スカラ座、バイエルン国立歌劇場、ウィーン国立歌劇場、メトロポリタン歌劇場などの名だたるオペラハウスに招かれています。なかでも緊密な関係を築いているバイエルン国立歌劇場からは宮廷歌手の称号を授与されています。
このアルバムはダムラウにとって初のクリスマス・アルバムとなりますが、その内容は豪華なもの。Disc1には作曲家のリチャード・ワイルズがオーケストレーションした多くのクリスマス・キャロルの数々。そしてDisc2には、バッハ、ヘンデル、モーツァルト、フランク、アダンのクリスマスに関連した作品のアリアを収録。オペラだけでなく、こうした選曲はダムラウの見識の高さ、そして彼女の声の持ち味を素晴しく発揮されており、特にクリスマスというキリストの誕生を祝う喜びの表現は絶品です!
※音楽を楽しく聴いていただきたいというディアナ・ダムラウの希望により、ブックレットには歌唱原語による歌詞カードは掲載しておりますが、他言語による対訳は掲載しておりません。よって日本語解説書にも、歌詞の日本語訳は掲載しておりません。(ワーナーミュージック・ジャパン)