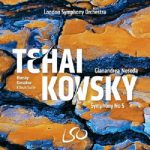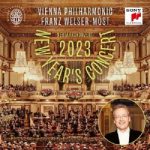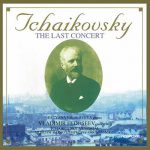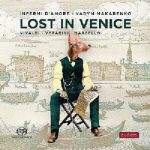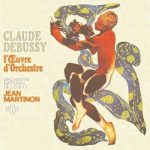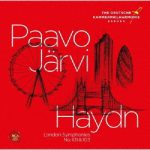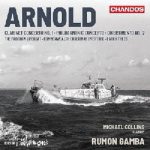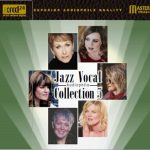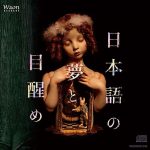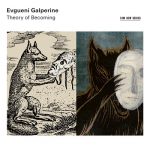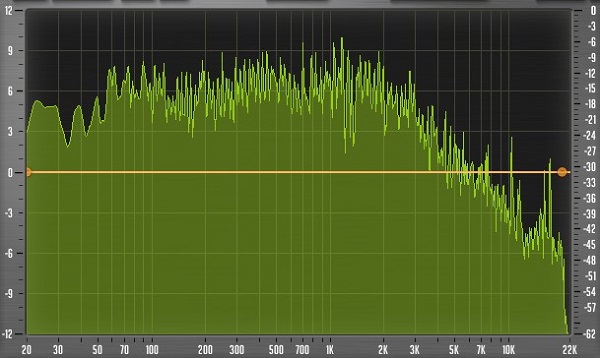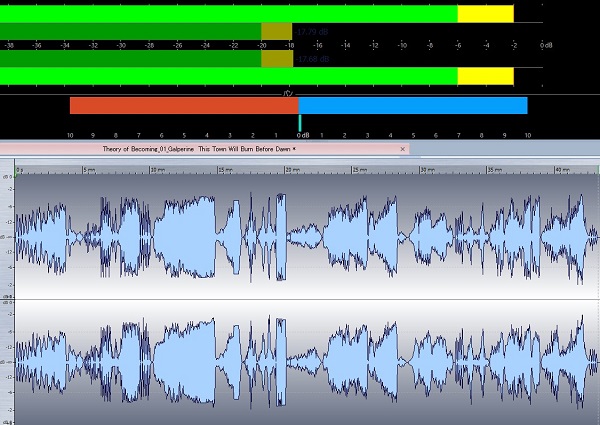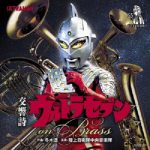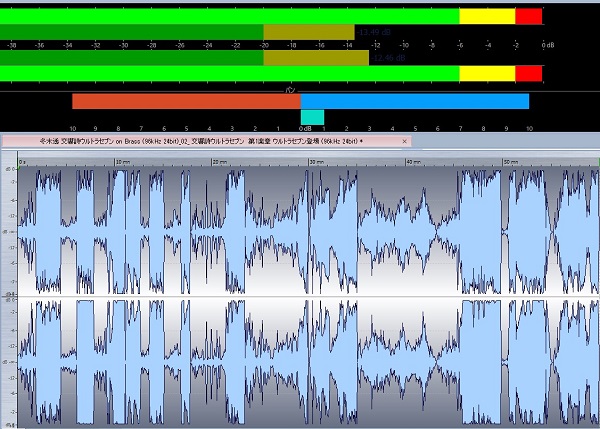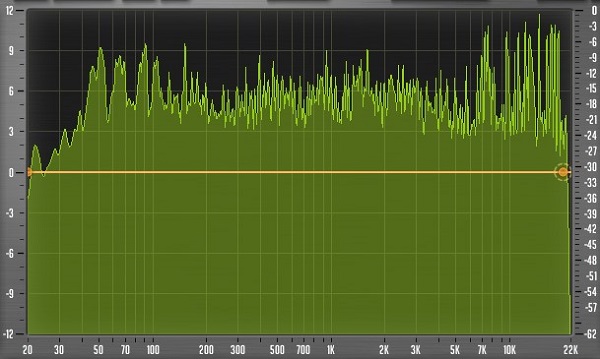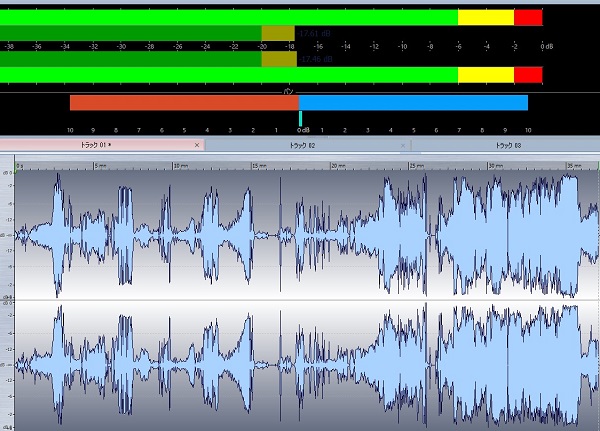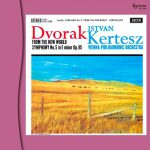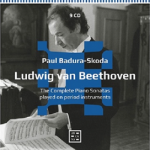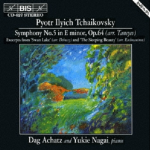Contemporary Records設立70周年記念作品!
伝説のサックス奏者ソニー・ロリンズがコンテンポラリーに残した名盤2作品『Way Out West』(1957年3月録音) 『Sonny Rollins and the Contemporary Leaders』(1958年10月録音)+コンテンポラリーに残したオルタネイト・トラック6曲をまとめた3枚組のボックスが登場。
コンテンポラリー・レコードの伝説的なエンジニア、ロイ・デュナンによって録音された作品をそのデュナンに師事し、今は世界的に評価のの高いマスタリング・エンジニアとなったBernie Grundmanがオリジナル・テープからリマスター。
グラミー賞受賞の音楽史家アシュリー・カーンによるソニー・ロリンズの2021年独占インタビューと新ライナーノーツを収録。
1957年に録音された不朽の名作「Way out West」は、ソニー・ロリンズをジャズのトップテナーサクソフォン奏者として確立した。ベーシストのレイ・ブラウン、ドラマーのシェリー・マンと共に、「I’m an Old Cowhand (From the Rio Grande)」、自身の「Way out West」、「There Is No Greater Love」、「After You’ve Gone」をベースにした高速ストンプ「Come, Gone」など、ロリンズがピークに達したときの演奏を聴くことができる。砂漠でウエスタン・ギアを身につけた(そしてテナーを抱えた)ロリンズのウィリアム・クラクストンによる写真も素晴らしい。
、翌1958年にコンテンポラリーレコードから次に出したアルバム『And The Contemporary Leaders』はソニー・ロリンズが3年で引退する前の最後のアルバムで、ピアニストのハンプトン・ホーズ、ギタリストのバーニー・ケッセル、ベーシストのリロイ・ビネガー、ドラマーのシェリー・マン(いずれもこの時代のコンテンポラリーレコードのバンドリーダー)と共に、この偉大なテナーによる、珍しいが刺激的なスタンダード曲の数々を聴くことができる。ロリンズは、”Rock-A-Bye Your Baby with a Dixie Melody”, “You”, “In the Chapel in the Moonlight”, そして “I’ve Found a New Baby” と “The Song Is You” の轟音ヴァージョンなどの曲で探索的かつしばしばウィットに富んだ即興を創造している。素晴らしい音楽だ。
最後のディスク「Contemporary Alternate Takes」は、2枚のアルバムからの抜粋の別ヴァージョンを収録。I’m an Old Cowhand”, “Come, Gone”, “Way Out West”, “The Song Is You”, “You”, “I’ve Found a New Baby” (80年代半ばに初公開)などは、クラシック・ヴァージョンに負けない “新ヴァージョン “である。
【パーソネル】Way Out West: Sonny Rollins(ts) Ray Brown(b) Sherry Manne(ds)
Sonny Rollins and the Contemporary Leaders:Sonny Rollins(ts) Hampton Hawes(p) Barney Kessel(g) Leroy Vinnegar(b) Shelly Manne(ds)
180g重量盤3LPボックス。
オリジナル・テープからバーニー・グランドマンがカッティング、RTIでプレス。ゲイトフォールド・チップオン・ジャケット仕様。